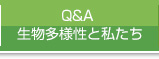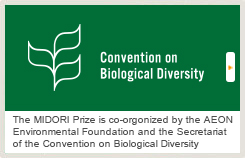風景を考える
- 港 千尋
- 美術家・映像人類学者、多摩美術大学情報デザイン学科 教授
2年ほど前から風景をテーマにした展覧会のシリーズを企画している。写真、絵画、ビデオやインスタレーションと、メディアを問わず、さまざまなアーティストに参加してもらい、アートを通して風景を考えようという展覧会だ。きっかけとなったのは、東日本大震災だった。瞬時に一変してしまった風景を前に、茫然自失となったあの日のことは一生忘れることはないだろう。わたしはその後福島県を中心にした被災地に足を運び、震災後の風景を記録するとともに、そこに生きる人々と対話を重ねながら、人間と土地との関係について思いをめぐらせてきた。今もつづく災害の余波のなかで、「風景」という日本語は、ますます重要な意味をもってきている。
風が運ぶもの
ふだんわたしたちが、風景画や風景写真というジャンルから思い浮かべるのは、主に16世紀から19世紀にかけて西欧に生まれ、少しずつ成熟していった、人間が土地へと向ける眼差しである。それは自分と世界のあいだに想像上の窓を設け、窓枠で切り取った世界の一部を、構図や遠近法といった視覚理論によってイメージへと変換する、高度に知的な作業をともなっていた。
ランドスケープという語は、ある場所に住み、そこに帰属する人間の集団と結びついた「ランドの形」を指している。それはランドスケープが英単語として現れた1600年前後の、土地の利用や利害関係を背景としているのであり、ランドスケープを描く画家も当然、その時代の土地と利用をめぐる政治学のなかで生きていた。フランス語のペイザージュが「国」や「農民」と語根を同じくするように、これらの語には人間の社会が概念的に含まれている。
いっぽうこれとは異質な成り立ちが、日本語の「風景」にはある。「景」という語は「光景」のように眺めるという点で、ある対象を見ている人間の存在が感じられるが、少なくとも「風」という語は、英語のランドスケープにも、フランス語のペイザージュにも見当たらない。風は「風土」や「風流」「和風」というように、気象としての風にとどまらず、非常に広い意味を派生させる語である。
風の字形を古くに遡ると、「鳳」すなわち伝説上の聖なる鳥が出てくる。また現在は使われないが、古代中国には数多くの異字があったことが知られ、同じ風でも、それが何を運んでくるか、あるいは何が運んでくるかによって異なる形を使っていた。風景の語には、鳥や虫をはじめ、目には見えない森羅万象を含んだ、大きな存在が含意されている。英語と日本語のあいだにあるこの違いは、人間が土地とのあいだに取り持つ関係は、ひとつではないということを示している。
西欧で風景画というジャンルが成立するのは宗教改革以後のことであり、市場経済に起きた変化とともに、静物画とともに登場した新商品という見方もできるだろう。いっぽう中国や日本では、市場経済のような外的関係よりも、自然と人間とのあいだに求められる内的関係のほうが重視されていた。なかでも重要なのは「気」という概念である。言うまでもなく気は自然のなかに流れるだけでなく、身体にも流れるものであり、しばしば書家や画家は自然との交感をとおして、気を調整することに長けたマスターと考えられていた。西欧と中国や日本を図式的に対立させる必要はないが、人間と自然とのあだに精神的なつながりを基本にすえていたことは、今日あらためて風景を考える上で忘れてはならない点であると思う。
対馬の天道地
風景は自然が人間とのあいだに開いた、一種の「対話」とも言えよう。あるいは読まれるべくして、そこに開かれている大部の書物である。ささやかな「読書」にも似た経験を、ある島の風景を例にして考えてみたい。
対馬は九州と朝鮮半島との間に浮かぶ島だが、その位置が示しているように、大陸から日本へと渡来したさまざまな文化が最初に通る、玄関口のような役割をしてきた。そしてここには大陸と日本の風景を考える上で興味深い、きわめて特殊な場所がそこに残っている。一般的に「天道地」と呼ばれる、聖域である。対馬には現在も「天道信仰」という土着の信仰が強く残っているが、それを実感するのが島の各地に点在する天道地である。鬱蒼と茂った森や山全体が天道信仰の対象で、しばしばそこには信仰の中心にある「天道法師」ゆかりの神社がある。
現在は下県郡の南端にある豆酘(つつ)と 上県郡の佐護が、二大中心地となっている。豆酘の 多久頭魂(たくずま)神社は龍良山(たてらさん)を遥拝する神社で、山がご神体である。神社の前には日本のコメの原種のひとつと言われる赤米を栽培する神田がある。毎年収穫した赤米を俵にするが、この俵じたいがテンドウと呼ばれる神として祀られる。また年末にはこの赤米を餅にして配り、それぞれの家ではこれを年神とする。多久頭魂(たくずま)神社が伝える赤米神事には、古代の穀霊崇拝が垣間見えている。
いっぽうこれと対をなすようにしてある島の北側、佐護(さご)の天神多久頭魂(あまのたくずま)神社のほうは、天道山を遥拝する。境内には石積みがふたつあり、神殿はない。天道信仰に関係のある神社はその多くが山をご神体とし、神社はあくまで遥拝のための祭祀場なのである。また対馬の北側には、毎年祭礼の日に石を積む神事があることが知られており、強風が吹きすさぶ海に向かって残る古い石積みを見ることができる。
天道信仰にまつわるさまざまな伝承は、13世紀以降密教や仏教など外来の宗教の影響も受けながら今日の形となったことが伺えるが、その始まりはおそらく自然そのものをカミとする信仰だったにちがいない。それは風景を読むことで感じられる。春先から夏にかけてこの島を巡ると、緑色の豊かさに心を奪われる。特に新緑の季節には、若葉が日の光を反射して黄金に輝くようだ。そうした山は、天道地の可能性が高い。というのも龍良山や天道山をはじめとする聖地は、人の立ち入りを認めず、たとえ村人が間違って入った場合にも枝一本、草一本持ち出すことを厳しく禁じてきたからである。
日本は昭和になって全国で植林を進めたが、対馬でも杉の人工林はそこかしこにある。古来の照葉樹林を伐採し、元々島にはなかった種だけを人工的に栽培した森である。遠くから見てもわかるくらい杉林は色が暗い。内部では鳥の声が聞こえず、気味が悪いという話をいろいろな人から聞いた。対馬の見事な照葉樹林は、もし天道信仰がなければどうなっていただろうかと、考え込まざるを得なかった。
来るべき知恵のために
このような木や石に人格をみとめ、それを神格化する信仰は一般的にアニミズムと呼ばれる。19世紀後半の人類学者エドワード・タイラーによって使われた呼称だが、人類学の父と呼ばれるタイラーはこれを土着民による低次元の信仰形態ととらえ、キリスト教に代表される高次の宗教へと進化する以前の未開宗教と考えた。今日ではもちろん、植民地主義的な見方は十分に批判されている。だがこれを社会進化論から取り外してみると、アニミズムは低次元の信仰などではなく、ひとつの知恵あるいは思想として、わたしたちにいくつものヒントを与えてくれるように思う。
たとえば大震災後、わたしたちは「文化と自然」という図式をよく聞くようになった。自然が引き起こした災害が、人間の作ったさまざまな文化を破壊したという、二項対立的な図式である。だが自然と文化は対立するものなのか、そもそも二分できるものなのだろうか。むしろ人間と自然はそれぞれの始まりから互いに深く結びつき、一種のネットワークを作ってきたのではないだろうか。とすれば「風」や「気」はそのような結びつきの表現だろう。
たとえば米に宿る神性が神事をとおして分配されるのも、ネットワークの一例である。天道に似たような自然信仰は、日本全国にその痕跡を残しているが、それらは長い時間をかけてひとつの風景を続かせるための、知恵であると解釈できる。長い時間とは、人ひとりの人生よりも長く、生産活動や為政よりも長い時間である。自然の循環的な時間に比べれば、ごく短い時間のなかで物事を判断せざるを得ない人間は、ある土地を続かせるための知恵を編み出さなければならない。わたしはこれまで地球の赤道地帯をはじめ、世界各地で自然と人間との関係を観察してきたが、このような知恵は二項対立的ではなく、人間が自分たちを含めた風景全体における、複雑な結びつきを維持するためのものではないかと気がついた。
震災で深く傷ついたこの社会が、結びつきを維持しようとすれば、相当知恵を絞らなければならないだろう。人間が風景を考えているとき、風景のほうも人間を考えているのだ。風景考は未来のアニミズムのための、一種の学校となるかもしれない。
港 千尋 (みなと ちひろ)氏プロフィール
美術家・映像人類学者。多摩美術大学情報デザイン学科教授。芸術人類学研究所所員。
群衆や記憶など文明論的テーマをもちつつ、研究、作品制作、展覧会、出版、キュレーション等、幅広い活動をつづけている。著作「記憶」でサントリー学芸賞、展覧会「市民の色」で伊奈信男賞を受賞。2007年にはベネチアビエンナーレ日本館のコミッショナーも務めた。2012年の近著に「ヴォイドへの旅」、「芸術回帰論」、「バスク七色」等がある。「風景考(Thinking Landscapes)」はSatoshi Koyama Galleryとの共同企画として続いており、2013年9月にはモンゴル・ウランバートルで開催される予定である。