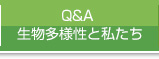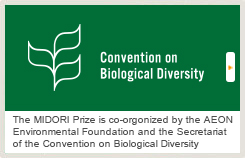次世代を守るグリーンインフラストラクチャー
- 鷲谷いづみ
- 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
最近、ヨーロッパ委員会は、「グリーンインフラストラクチャー(緑のインフラ)」を積極的に利用していくための戦略を採択した。緑のインフラは、空間計画(土地利用計画)において、自然のプロセスを十分に理解したうえで尊重する手法であり、生態的、経済的、社会的な利益をできるだけ多く確保することをめざす。例えば洪水防止には、従来のようなダムや堤防などの建設に代え、大雨の際の水をスポンジのように吸収する効果を発揮する湿地を活用する。湿地は、二酸化炭素の吸収源となり生物多様性の維持に大きく貢献するだけでなく、水質浄化、緑地として、バードウォチングなどの自然とのふれあい活動をはじめとする多くのレクリェーションの機会を提供する。経済的コストも環境のコスト(環境負荷)も小さい一方で、多様な利益が得られる。総合的な費用対効果が大きいことから、「合理的な判断」にもとづく選択が保障されれば、当然選択されるべき手法である。
2010年10月に日本で開催された生物多様性条約COP10において、新しい戦略計画(2020年までに達成すべき愛知目標を含む)が策定されたことをうけ、ヨーロッパ連合は2011年の5月に新しい「生物多様性戦略」を公表した。COP10で採択された世界の新戦略計画では2050年までの長期目標であるビジョンを、日本の提案を受けて「自然と共生する世界」と定めたが、EUの戦略は、それよりも具体的なビジョンを掲げている。すなわち、「2050年までにEU領域の生物多様性とそれが提供する生態系サービス-その自然資本-が、生物多様性の存在価値(intrinsic value)と人間の豊かな暮らし(human wellbeing)と経済的な繁栄への貢献ゆえに、保護され、価値を認められ、それによって、生物多様性の損失を原因とする破局的な変化を回避できる」というものである。
この長期的な目標へ寄与する手段として位置づけられたのが緑のインフラである。緑のインフラは、連結性(開発により分断化されたランドスケープにおける生態系のつながりや生物の種間関係などの健全なあり方)の保障された健全な生態系を確保することを通じて生物多様性の保全に寄与するのみならず、水の浄化、生産性の高い土壌の維持、質の高いレクリェーションの機会の提供などの生態系サービスを介して地域社会に利益をもたらす。
ヨーロッパ連合の緑のインフラに関する「戦略」では、都市、田園地域の別を問わず、人々の豊かで健やかな暮らしにとって自然がいかに重要かを強調している。全体として、ヨーロッパ連合が、生態系のはたらきを保全・回復することに強い関心をもっていることを示している。生態系の健全なはたらきを発揮できるように手助けする緑のインフラは、経済的にみて、整備段階でもメンテナンスにおいても、他の手法と比べて格段に安上がりである一方で、同時に多様な利益が得られることはすでにのべた。それは、社会全体にとって大きな魅力となる。投資される費用の多くが調査・モニタリングおよび管理作業のための人件費であり、長期的にみた雇用創出の効果が大きく、地域にとっての利益が大きい。
緑のインフラは、1990年代半ばにアメリカ合衆国で意識化された社会インフラの手法である。それは、土地利用において自然環境を十分に活かす計画手法であり、「生命維持」機能を高めるための生態系のネットワークを重視するところに特徴がある。北アメリカでは、1990年代にすでにその方向への舵が大きく切られ、大規模ダム建設の時代は終わりを告げた。それ以前からはじまっていた河川や大湿地帯の自然再生事業も含め、多くの緑のインフラの事業が実施されている。
大震災後の日本では、このような国際的な動向とは真逆の方向にインフラ整備が進められようとしているかにみえる。利根川流域の河川整備計画において、一度は中止の意思決定がなされるかにみえた八ッ場ダムの建設も復活した。国際的にみればアナクロニズムといわなければならないこのような事態が生じている理由は、どこになるのだろうか。おそらく、政策決定者をはじめとする社会全体の生物多様性や生態系、すなわち自然環境に対するリテラシーがきわめて低い水準にとどまっていることによるのだろう。しかし、かつての日本では、独自の智惠にもとづく伝統的な「緑のインフラ」がむしろ一般的であった。里地里山(さとやま)の土地利用そのものが模範的な緑のインフラといえるからである。
さとやまには、農地とともに、建材、飼料、肥料とする生物資源や稲作のための水資源を確保するための空間、すなわち、樹林、草原、湿原、水辺等がふんだんに存在した。河川の氾濫原のヨシ原やオギ原は茅など生物資源の採集地として利用されたが、そこは同時に、風水害などの災害から集落や農地を守る干渉帯の役割も果たしていた。
地形に応じて河口に発達する干潟は、魚介類などの自然の恵みを育むとともに水質浄化など、多くの生態系サービスを提供していた。そのような場所が開発され、市街地になったり人間活動が活発な場所となると、自然災害の可能性が拡大した。
緑のインフラで確保された空間を、栽培しなくとも自然に旺盛に生育する植物のバイオマス資源などの採集場所としたり、広大な風景や生物多様性の豊かさゆえのレクリェーションを楽しんだり、水質浄化の機能を活かすなど、多様な生態系サービスを享受する場として用いれば、たとえ風水害や津波に襲われても、人命や財産などが失われたり人間活動に大きな支障が生じるような「災害」がもたらされることはないはずである。
「干渉空間」の確保につながる緑のインフラは、固い人工構造による対策、「灰色のインフラ」に比べて、社会が負担すべきコストが小さくて済むこともすでに述べた。コストについては、建設費、用地取得費などの貨幣価値で測れるコストだけでなく、生態系の機能を妨げるような不可逆的な環境変化をもたらさない、といった環境コストを見積もることが特に重要である。一方で、多様な生態系サービスを提供するポテンシャルを得られる便益として算入する必要がある。そのように的確にコストと便益が見積もられれば、居住地などに災害がもたらされることがないよう自然地を緩衝地帯として十分に確保するという防災・減災の手法は、長期的にみてもっとも効率的、効果的な手法であることが示されるだろう。そのことは、ミレニアム生態系評価の報告書や生物多様性条約関連の評価文書など、国際的な環境評価の文書において繰り返し主張されていることでもある。
干潟やヨシ原やオギ原などバイオマスエネルギー材料として期待されているイネ科多年草が優占するウェットランドの再生は、生物多様性の保全・回復効果を期待できるだけでなく、メンテナンスフリーで多様な生態系サービスの供給ポテンシャルを維持し、必要に応じて持続的に利用できる生態系を蘇らせることでもある。このことについては拙著「震災後の自然とどうつきあうか」(岩波書店)に詳しく述べた。
日本においても、灰色のインフラ一辺倒から脱して、伝統的なさとやまの緑のインフラに学び、国土の自然的・社会的条件に適合した新たな緑のインフラが発展させることが望ましい。
写真1 大規模な緑のインフラ再生プロジェクト: 英国のグレートフェンプロジェクト
多様性の高いモザイク自然
写真2 大規模な緑のインフラ再生プロジェクト: 英国のグレートフェンプロジェクト
科学研究に基づく管理は原種に近いウシも利用
写真3 さとやまの水辺
写真4 久保川イーハートーブ自然再生の対象地域のため池
鷲谷いづみ (わしたに いづみ)氏プロフィール
1950年生まれ。1972年、東京大学理学部生物学科卒業。1978年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了(理学博士学位取得)。1986年より1992年まで筑波大学生物科学系講師、1992年から2000年まで筑波大学生物科学系助教授。2000年より東京大学大学院農学生命科学研究科教授 現在に至る。日本学術会議会員 中央環境審議会委員。
1997年 第5回花の万博記念奨励賞受賞、2008年 平成20年度 環境保全功労者 環境大臣表彰、2013年 第7回みどりの学術賞受賞。
専門は生態学、保全生態学で、現在は生物多様性と自然再生に係わる幅広いテーマの研究に取り組んでいる。
主な著書:
『保全生態学入門』(文一総合出版)、『自然再生 持続可能な生態系のために』(中公新書)、『天と地と人の間で』(岩波書店)、『生物保全の生態学』(共立出版)、『生態系を蘇らせる』(NHK出版)、『コウノトリの贈り物』(地人書館)『絵でわかる生態系のしくみ』(講談社)、『にっぽん自然再生紀行』(岩波書店)『地球環境と保全生物学』(岩波書店)、『岩波ブックレット <生物多様性>入門』(岩波書店)、『セイヨウオオマルハナバチを追え-外来生物とは何か-』(童心社)、岩波ジュニア新書 『さとやま - 生物多様性と生態系模様』(岩波書店)、『震災後の自然とどうつきあうか』(岩波書店)他多数。