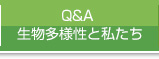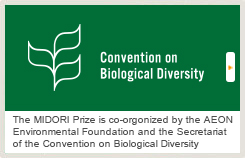日本とチリ: 津波で結ばれた国
- フアン・カルロス・カスティーリャ
- チリ カトリカ大学 名誉教授、2012年 The MIDORI Prize for Biodiversity 受賞者
日本とチリは、いずれも「環太平洋火山帯」に属する国である。この火山帯では、深く沈み込んだ海洋域に沿って、地殻プレート同士がぶつかり、世界の地震の約90%が起きている。また、地球上の津波のほとんどがここで記録されている。そのため、両国は地震や津波災害という点で多くの共通項があり、まさしく「津波で結ばれた国」と言うことができる。日本とチリの間には、津波被害にまつわる一種の連帯感がある。とはいえ、日本とチリの連帯感と友情は長年にわたるものであり、自然災害という共通項をはるかに超えて続くものだ。
 チリでは、2010年2月27日にチリ中部のマウレ州で発生したマグニチュード8.8の大地震とその後に沿岸部を襲った津波災害(「27F」と呼ばれる)から、今年で5年を迎える。偶然にも、日本も、2011年3月11日に発生して15,000人以上の命を奪ったマグニチュード9.0の東日本大震災と最悪の津波被害から、4年を迎える。これは日本とチリにとって、被害を思い起こすだけでなく、海沿いの漁村に対する津波の影響、海洋自然、学んだ教訓、そして何よりも相互協力を強化する方法について考える特別な機会かもしれない。
チリでは、2010年2月27日にチリ中部のマウレ州で発生したマグニチュード8.8の大地震とその後に沿岸部を襲った津波災害(「27F」と呼ばれる)から、今年で5年を迎える。偶然にも、日本も、2011年3月11日に発生して15,000人以上の命を奪ったマグニチュード9.0の東日本大震災と最悪の津波被害から、4年を迎える。これは日本とチリにとって、被害を思い起こすだけでなく、海沿いの漁村に対する津波の影響、海洋自然、学んだ教訓、そして何よりも相互協力を強化する方法について考える特別な機会かもしれない。



 簡単な言葉で説明するなら、津波とは、主に地震によって引き起こされる自然現象であり、海水を垂直方向に押し上げ、それによって膨大なエネルギーを持つ波を生み出すものである(すべての海底地震が津波を引き起こすわけではない)。津波は、人為的災害ではなく、地球に起こる自然現象である。現状の理解では、世界の気候変動や生物多様性の喪失とは異なり、津波は社会的(人為的)に引き起こされた環境変化とは無関係である。つまり、津波(および地震)は、何千年、何百万年にわたって、日本とチリ、そして環太平洋火山帯において繰り返し発生し、今後も発生するものだ。
簡単な言葉で説明するなら、津波とは、主に地震によって引き起こされる自然現象であり、海水を垂直方向に押し上げ、それによって膨大なエネルギーを持つ波を生み出すものである(すべての海底地震が津波を引き起こすわけではない)。津波は、人為的災害ではなく、地球に起こる自然現象である。現状の理解では、世界の気候変動や生物多様性の喪失とは異なり、津波は社会的(人為的)に引き起こされた環境変化とは無関係である。つまり、津波(および地震)は、何千年、何百万年にわたって、日本とチリ、そして環太平洋火山帯において繰り返し発生し、今後も発生するものだ。
それが地震と津波災害に対する適切かつ唯一の心構えだと、私には思われる。そして私たちは、こうした災害の被災者の方たちのことを真っ先に考えなければならない。災害の影響と人的被害を減らすためには、何が必要か? より科学的に言えば、技術的進歩と社会的進歩が間違いなく必要である。地震と津波は、これからも日本とチリ、そして環太平洋火山帯の国々を襲う。それらは環境の一部であり、適切かつ早期の予測につながる知識と災害に対する社会の備えが、災害に立ち向かうための唯一の手段である。そして、その手段をさらに発展させ、各国の間で共有する必要がある。事実、日本とチリの間には、これらの災害に長年直面してきた経験を踏まえ、相互の学習と進歩のために共同で行えることがたくさんある。しかし、それは行われているだろうか? それが適切に行われているかどうかは、疑問である(間違っているかもしれないが)。私の知る限り、たとえば地球物理学や工学などの分野では、科学的協力が十分に行われているようだ。しかしながら、海洋学、生態学、海洋保護および修復、教育、アウトリーチ活動、社会科学、人々の備えにおいては、十分とは言えないようだ。日本は、地震予測による早期警戒において技術的にチリよりはるかに進んでいる。私は、そのような技術がチリでも実施されることを願っている。とはいえ、問題は技術だけではない。社会の備え、科学、教育、法整備も重要な問題であり、日本とチリが相互利益のために共有するべきことはたくさんある。私の意見では、私たちは機会を十分に活用していない。たとえば、チリの側から見れば、チリと日本の地域社会(小規模な漁村)に「土着の生態学的知識(LEK)」として根付いている地震・津波経験から、互いに多くのものを学ぶことができると思う。そうした情報を比較することで、災害への備えを強化することができるだろう。また、海洋学的進歩、安全な建築基準および免震技術においても協力の余地がある。さらに、一般へのアウトリーチ活動と学校教育の分野は、津波災害の影響に立ち向かうために不可欠である。日本とチリは、これらの苛酷な自然災害に対する備えを強化し、双方にメリットをもたらす対策に向けて、十分に協力しているだろうか? この点は疑問である。日本とチリの行政当局、NGO、ビジネス界、産業界、寄付者、財団法人、有識者、一般の人々が力を合わせて取り組むべき課題が、そこにある。これらの課題に対して、多くのことが行えるであろうし、行わなければならない。
 その一方で、自然の海洋生態系および生物多様性に対する地震や津波の影響を緩和するために私たちができることは、ほぼ皆無である。したがって、私の経験では、沿岸で地震や津波の被害が起きた後に、生態系への影響に対処するには、自然個体群および集落の自然な回復を待つか、あるいはより困難ではあるが、復元を行うしかない。最終的には、被災地環境の生態系レジリエンスによって行く末が決まるだろう。もちろん、津波後の沿岸部の海洋環境において、早急に実行するべき最も重要な活動のひとつは、被災区域の海底および海水中の瓦礫と汚染物質を除去することである。チリでは、27Fの後、フアン・フェルナンデス諸島(27F津波により甚大な被害を受けた)の潮間帯および海中の瓦礫除去において、大きな経験を積んだ。これを、日本の行政機関や科学者にも伝えることができるだろう。また、日本も、チリの行政機関や科学界と共有できる豊富な経験を有している。
その一方で、自然の海洋生態系および生物多様性に対する地震や津波の影響を緩和するために私たちができることは、ほぼ皆無である。したがって、私の経験では、沿岸で地震や津波の被害が起きた後に、生態系への影響に対処するには、自然個体群および集落の自然な回復を待つか、あるいはより困難ではあるが、復元を行うしかない。最終的には、被災地環境の生態系レジリエンスによって行く末が決まるだろう。もちろん、津波後の沿岸部の海洋環境において、早急に実行するべき最も重要な活動のひとつは、被災区域の海底および海水中の瓦礫と汚染物質を除去することである。チリでは、27Fの後、フアン・フェルナンデス諸島(27F津波により甚大な被害を受けた)の潮間帯および海中の瓦礫除去において、大きな経験を積んだ。これを、日本の行政機関や科学者にも伝えることができるだろう。また、日本も、チリの行政機関や科学界と共有できる豊富な経験を有している。

このコラムでは、「自然」、「生態系機能」、「生態系サービス」という概念が持つ学術的効果とコミュニケーション効果を、私が信奉しているということを強調したい。そして、それらの概念のベースに生物多様性があることは間違いない。実際、私は海洋学者として、沿岸生態系または少なくともその一部が果たしている機能を理解したいと考えている。自身の分野研究として、1985年と2010年のチリ地震の後に、沿岸部の地盤が約0.8~3メートル(潮汐系においては約1.5メートル)隆起したことを観測し、沿岸部の岩礁性潮間帯のレジリエンスの監視(モニタリング)を行い、結果を発表した。ここから、「これらの生態系のレジリエンスは、どれほど高いか?」、「それらが再び機能を回復する、または新たに置き換わるには、どれほどの期間がかかるか?」といったことが主要な課題となるとわかった。かいつまんで説明すると、この場所での生態系のレジリエンスは非常に高かったため、約2~3年で生態系機能が回復し、主要な一次生産者、草食動物、肉食動物、濾過摂食者の完全な自然回復が見られた。その一方で、27Fによる沿岸部の劇的な地盤隆起の後に、小規模な海面養殖による重要な海藻資源の一部が完全に姿を消したという例もある。これらは、もう復活することはないだろう。要するに、地震によって海岸が劇的に変化し、海藻の生息環境が失われたのである。また、27F津波の後、いくつかの海底集落(水深約20~25メートル)が、岩の移動、堆積物の流動、その他の海底攪乱効果により影響を受けたことも示されている。にもかかわらず、これらの地域における主要な底生漁業(*)は影響を受けていないようである。この場合、生態系サービス(漁業)と底生漁業の機能によるアウトプットに焦点を当てた上で「地域の底生漁業は影響を受けたか、否か?」と問うことが、主要な課題となる。その答えは「ノー」であるようだ。そして最後に、私たちはいくつかの学際研究を行い、小規模な漁村の暮らしと、震災の影響に取り組む社会組織について調べた。この研究は、生物学、生態学、社会科学という分野を統合して行われた。土着の知識、コミュニティの住民の認識や希望が、地震と津波によってどのように影響を受けたかを理解することが、調査の主眼である。私たちは、その成果を日本の科学者とも共有したいと思っている。
*底生漁業とは、ウニ、軟体動物、藻類等の資源を採取する漁業法。ダイバーによる潜水採集が主流。国家統計によると、その量は数千キログラムに相当するといわれている。チリでは年間にしておよそ3万トンのウニを採取しており、その多くは日本に輸出されている。
要約すると、地震と津波は、自然、生態系、生物多様性に影響を及ぼす、言い換えれば「私たちとその環境に影響を及ぼす」自然災害である。凄まじい津波は自然全体に影響を与え、密接に絡み合う社会的・生物的・物理的な複合的機能に影響を及ぼす。私に言わせれば、これらすべてが「自然」と呼ばれるものであり、人類はそのなかで最も重要な構成要素のひとつである。したがって、少なくともチリにおいて(おそらく日本においても)、私たちが本当に必要としていることは、さらなる科学的進歩を遂げ(とりわけ各分野の統合において)、地震と津波のより高度な早期予測技術の開発を目指し、海洋環境への影響と生態系のレジリエンス、機能、生物多様性について科学的理解を深めることだと思われる。そして、教育、アウトリーチ活動、法整備においてもさらに前進し、津波の影響に立ち向かう社会の備えを強化することである。
日本とチリは津波で結ばれた国同士であるという認識は、これからも津波に見舞われる運命にある両国の間で、長期にわたる友好と協力を強化する役割を果たすだろう。さあ、力合わせて津波に立ち向かおう!
フアン・カルロス・カスティーリャ氏 プロフィール
フアン・カルロス・カスティーリャ(1940年生まれ)は、天然資源の持続可能な利用を行う上で重要となる禁漁区および管理水域の研究で知られている。「南米における海洋生態学のパイオニア」と言われるカスティーリャは、カトリカ大学生態学部の教授として海洋生態学、群集生態学を教えているほか、25年以上前に禁漁区研究の拠点となったチリのラスクルーセスにある沿岸海洋調査ステーションの局長を務めている。
禁漁区での長期的研究において、カスティーリャは「人間が除外された」禁漁域および季節的な禁漁を調べるため、地域の漁協と協力して実験を行った。カトリカ大学実験所に作った小規模海洋保護区を通じて、海洋保護区が周辺海域の資源の増産や生物多様性の保全につながることを科学的に証明、この成果をもとに、小規模海洋保護区と持続可能な漁業の組み合わせを提唱し、チリ全体に広めた。
こうした取り組みは、チリの漁業・養殖業法、とりわけ底生生物資源の管理に大きな影響を与えただけでなく、資源の持続的利用と沿岸生態系の保存において零細漁業が果たす役割を明確にし、チリ沿岸地域での零細漁業を保護する制度をチリで実現した。また、Jane Labuchenko教授、Bruce Menge教授、Steve Gaines教授らチリやアメリカの研究者とともに、PEW財団海洋保全プロジェクト、メロン財団沿岸生態系プロジェクト、沿岸海洋学際研究パートナーシップ等の事業に参画しており、これらのプロジェクトについて60以上の論文を発表している。
こうした活動は、沿岸所有権や管理・開発水域、共同管理に関連したカスティーリャの理論と実践により高い成果をあげている。また、生物多様性の保全と持続的利用の両立において、零細漁業の役割を世界で認知させ、生物学だけでなく新たな法制度の提案までを担ったことは、世界における生物多様性に関する取り組みにおいて発展的な影響力を持っている。
現在、30以上の大学に招聘され、講義やセミナーを行っており、250以上に及ぶ論文を発表している。また、海洋公園ならびに保護区に関する先駆的な活動、沿岸資源の共同管理、海洋生物多様性の保全における業績が認められ、The MIDORI Prize for Biodiversityを含む数々の賞を受賞している。